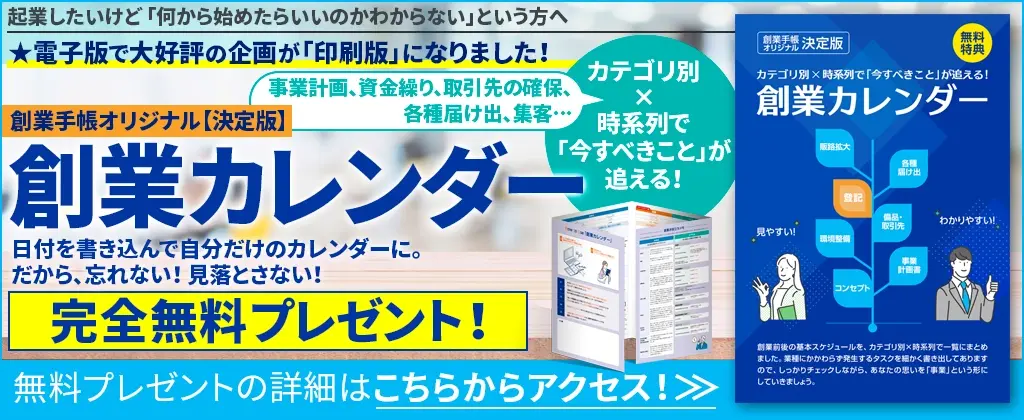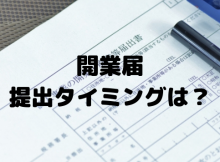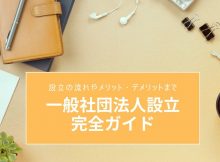【2025年最新版】合同会社と株式会社の違いを徹底比較!メリット・デメリットや選び方をわかりやすく解説
合同会社ってどう?株式会社との比較も交えて選定を

昨今「合同会社」を選択する場合も増加してきています。創業手帳は株式会社ですが、創業者の大久保は合同会社を設立した経験もあります。
実際に設立した経験をもとに、合同会社とはどんな法人形態なのか、メリットやデメリットもわかりやすくまとめました。よく比較される株式会社との違いも要チェックです。
合同会社での起業に必要なのはズバリ情報収集です。まずは創業手帳(無料)を読んで起業前後にやるべきことをインプットしましょう。融資から税金、ビジネスノウハウまで、一冊に集約しました。
起業の準備は多岐にわたるため、煩雑になりがちです。無料の創業カレンダーを使えば、以下のようなカレンダー形式でいつなにをすべきかが一目瞭然になり、起業の準備がスムーズに進みます。

創業手帳 株式会社 ファウンダー
大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
【比較表】合同会社と株式会社の違い
株式会社と合同会社の主な違いは「経営と出資の関係」や「組織のあり方」にあります。
とくに所有と経営の分離の有無/資金調達の選択肢/意思決定の仕組みに注目すると、自分に向いている会社形態を判断しやすくなります。
合同会社から株式会社に移行することも可能ですが、手続きが煩雑で資金調達のタイミングを逃すリスクもあります。最初から違いをよく理解して選ぶことが重要です。
所有と経営の分離の有無(基本的な性質の違い)
| 比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 資本金 | 1円~ | 1円~ |
| 設立人数 | 1人~ | 1人~ |
| 設立費用 | 約6万円~ | 約17 5万円~ |
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 経営者 | 出資者=社員 | 株主が選定 |
| 代表者肩書 | 代表社員 | 代表取締役 |
| 利益配分 | 原則自由(定款で決定可) | 株数に応じて配分 |
| 決算公告 | 不要 | 必要 |
合同会社は出資者=経営者で、所有と経営が一致。株式会社は株主と経営者が分かれ、ガバナンス重視の形態です。
資金調達の選択肢の違い
| 方法 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 社債発行 | 〇 | 〇 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | × | 〇 |
| 新株発行 | × | 〇 |
| 金融機関からの融資 | 〇 | 〇 |
| 個人・法人の出資 | 〇 | 〇 |
| ベンチャーキャピタル投資 | ×(一部例外あり) | 〇 |
| 株式上場 | × | 〇 |
| M&A | 〇 | 〇 |
株式会社の方が資金調達の手段は幅広く、事業拡大や採用強化を目指す企業に選ばれやすいです。
一方、合同会社は融資やクラウドファンディングなど小回りの利く調達手段が中心で、少額資金で始めやすいのが特徴です。
意思決定の仕組みの違い
-
- 合同会社:社員全員の合意や多数決で決定。出資比率に左右されず、柔軟でスピーディー。
- 株式会社:株主総会での決議が必要。時間やコストはかかるが、株主の意見を反映できる。
信頼性・知名度の違い
-
- 合同会社:制度が新しいため知名度は低め。「代表社員」という肩書が伝わりにくい場面もある。
- 株式会社:社会的信用が高く、法人営業や採用に有利。
設立費用や維持コストの違い
-
- 合同会社:設立費用6万~と、維持コストも低い(定款認証・決算公告不要、役員任期なし)。
- 株式会社:設立費用16.5万円以上、公告義務や役員変更登記など維持コストがかかる。
どんなケースに向いているか(小規模向き/大規模向き)
| 比較項目 | 合同会社に向くケース | 株式会社に向くケース |
|---|---|---|
| 顧客層 | 個人中心、少人数取引 | 法人中心、大規模取引 |
| 事業の主体 | 人やスキルが中心 | 商品や仕組みが中心 |
| 費用負担 | 低コスト重視 | 拡大を見据え多少は許容 |
| 事業規模 | 小~中規模 | 中~大規模 |
| 多額の資金調達 | 不要 | 必要 |
| 上場の希望 | なし | あり |
小規模スタートや個人事業からの法人成りは合同会社が適し、将来の上場や大規模展開を狙うなら株式会社が適しています。
小規模ビジネス・スモールスタートなら合同会社、拡大・上場を目指すなら株式会社など、 起業家のライフプラン別の選び方ができます。
現状だけではなく、将来的な展望も踏まえて選ぶのがポイントです。
創業手帳のこれまでの経験から、事業拡大を狙っていたり、採用を進めたりしたい企業は株式会社を選ぶ傾向です。
資金調達の予定がなくても、多くの場合は社会的な信頼性の面から株式会社を選んでいます。
資金調達のメリットより、経営の自由度などを優先したい場合は合同会社を選ぶ意義が大きいでしょう。方針が変わった際には、株式会社への変更も可能です。
合同会社とは?特徴などを解説

合同会社は、2006年の会社法施行によって新たに作られた法人形態で、合資会社・合名会社とならぶ持分会社の一種です。1977年にアメリカで誕生した法人形態で、「LLC(Limited Liability Company)」とも呼ばれます。
合同会社の特徴を以下の表にまとめました。
| 設立費用 | 6万円程度 |
|---|---|
| 出資者が負う責任 | 出資額を上限とした有限責任 |
| 役員の任期 | 決まっていない |
| 経営権の所在 | 出資者(経営者および社員と同一)にある |
合同会社は小さなスケールで始めやすい会社形態です。設立費用の安さ、経営の自由さなどから、意思疎通がしっかりできる仲間内や個人での会社立ち上げに向いています。
なお合同会社とは持分会社の一つです。会社の種類は会社法において「株式会社」と「持分会社」の2種類に分けられるほか、組織形態の分類としては「一般社団法人」「NPO法人」もあります。
設立費用
合同会社を設立するには約6万円程度が必要です。主な費用には次のものがあります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | いずれか高いほうの金額
・資本金額 × 0.7% ・6万円 |
| その他 | 法人印鑑の作成:4千円~(必要に応じて) |
| 合計金額 | 6万円~ |
登録免許税とは登記手続きにかかる税金です。資本金100万円の場合0.7%をかけると7,000円なので、登録免許税は6万円になります。
会社の設立には必ず定款を作らなくてはなりません。ただし、合同会社は他の株式会社や一般社団法人などとは異なり定款の公証人の認証は不要のため、認証費用は不要です。
オンラインで登記申請をする場合は印鑑届出書が不要なため、法人印鑑は会社設立には必須ではありません。ただ、銀行口座の開設や契約書の押印など、会社運営をするなかで必要になるケースが多いでしょう。
これまで合同会社を設立した経験から、実際には専門家にサポートを受けたほうがいいため、サポート費用を上乗せした10万円までを目安としています。
出資者が負う責任
合同会社の出資者は、出資額を上限とした有限責任を負います。有限責任であるため、例え出資額では足りない負債を会社が抱えたとしても、出資者個人が抱えることはありません。
有限責任とは反対に無限責任の会社形態もありますが、この場合は出資額以上の負債が発生すると個人の財産にも影響を及ぼします。
合同会社と比較されやすい株式会社も有限責任です。いずれも責任は出資額までにとどまるため、リスク管理がしやすくなります。
役員の任期
合同会社は役職の任期についての規定がなく、同じ人物が何年も役員でい続けられます。役員の氏名や役職が変わらない限り、登記変更は不要です。
なお、合同会社の役職とは株式会社の役員と同じものです。
経営権の所在
合同会社では、経営権を持つ「経営者」「出資者」「社員」が同一です。出資者は経営者でもあり、社員でもあります。株式会社でいうところの株主と同じです。
出資額に関わらず1人1票の議決権を持つため、出資金額による力の差はなく多数決で意思が決まります。
出資額は会社の持ち分比率に影響を与えるものの、株式会社のように保有株、つまり出資額で経営権の所在が変わることはありません。
株式会社とは?特徴や仕組みを解説
株式会社は、日本で最も設立件数が多い会社形態であり、株主が出資し、経営は取締役が担う仕組みを持ちます。ここでは、その特徴や基本的な仕組みを分かりやすく解説します。
株主と経営者の分離
株式会社の大きな特徴は「所有と経営の分離」です。株主は会社に資金を出資しますが、日々の経営に直接関与する必要はありません。
経営は取締役や経営陣が担い、株主は株主総会を通じて取締役の選任や解任に関与します。
これにより、出資者は経営の専門知識がなくても会社の成長に参加でき、経営者は事業運営に専念できます。株主は株式保有比率に応じて利益配当を受け取る仕組みとなっており、リスクとリターンを明確に分けられる点も特徴です。
代表取締役と取締役会
株式会社の経営を実際に動かすのは取締役と代表取締役です。取締役は株主総会で選任され、取締役会を構成して会社の重要事項を決定します。その中から選ばれる代表取締役が、会社の顔として契約や業務執行を行います。
取締役会を設置するかどうかは会社の規模によって異なりますが、中規模以上の株式会社では一般的に導入されています。意思決定のプロセスを複数人で担うことで、経営の透明性や健全性を高められる点が特徴です。
株式による資金調達
株式会社は、株式を発行して投資家から資金を集められる仕組みを持っています。株主は出資額に応じて株式を取得し、配当や株価の値上がりによる利益を得られます。
会社側は銀行融資に依存せずに多額の資金を調達できるため、事業拡大や新規プロジェクトへの投資がしやすいのが特徴です。特に上場企業の場合は、証券市場を通じて不特定多数の投資家から資金を集められるため、大規模な成長を可能にします。こうした仕組みは株式会社ならではの強みです。
合同会社のメリット・デメリット
合同会社のメリット・デメリットは以下になります。詳しくは後ほどご説明していくので、先に一覧で確認しましょう。
| メリット | ・設立費用が株式会社より少ない ・会社の維持コストが低い ・出資者のリスクヘッジができる ・議決権や配当が出資額に左右されない ・組織運営の自由度が高い ・法人化の節税効果を得られる |
| デメリット | ・資金調達の選択肢が少ない ・出資者の関係構築が必要になる ・知名度・認知度が低い ・権利譲渡・相続・事業承継がしにくい |
メリット
まずは合同会社を設立するメリットから解説していきます。
設立費用が株式会社より少ない
合同会社は株式会社に比べて設立費用が安く済みます。費用がもっとも安く済んだ場合で比べてみましょう。
| 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|
| ・登録免許税:6万円~ | ・登録免許税:15万円~
・公証人による定款認証:資本金により1 ・定款の印紙代:0円(紙定款は4万円) |
| 合計:6万円~ | 合計:16.5万円~ |
どちらの会社でも主な費用は登録免許税で、株式会社は安くても16.5万円です。合同会社の2倍以上を払わなくてはなりません。
なお、創業手帳の創業者である大久保は、起業家の負担を軽減するために内閣府の委員として起業に係る制度設計への助言をしていますが、まだまだ費用面でのハードルがあるのが実情です。
会社の維持コストが低い
合同会社は会社の維持コストが低い傾向にあります。特に株式会社と比べると、決算公告の義務がない、役員の任期に決まりがないといった点で有利です。
決算公告とは決算内容を公開することで、決算書の準備や公告に伴う費用がかかります。任期を終えた役員の登記を変更する際にも、選定の手間や登記費用を見込んでおかなくてはなりません。
合同会社ではこうしたコストを抑えられるため、リソースの少ない会社でも維持しやすいメリットがあります。
出資者のリスクヘッジができる
合同会社の出資者は全員が有限責任者です。出資額以上の責任を負うことはないので、リスクヘッジできます。
仮に個人事業主(フリーランス)のまま事業を立ち上げて失敗し、出資額以上の負債を抱えると、すべて個人で返済しなくてはなりません。
よく会社のほうがリスクが高く、個人事業主のほうがリスクが低いと思われがちですが、法律的な実態では逆です。合同会社のほうがリスクの範囲が有限なので、事業を中断しても個人で責任を取る必要がなく、経営者が守られます。
議決権や配当が出資額に左右されない
合同会社の出資者が得られる議決権や分配利益は、出資額に左右されません。
議決権は原則1人1票、分配利益は会社によって決めておけます。いずれも定款で設定し、変更も可能です。
たとえば「出資金額にかかわらず均等割」「利益に貢献した人に加重して配分」など、会社の事情に応じて考えることができます。
複数の経営者がいる場合も、出資額の差で経営バランスが崩れる心配がありません。
組織運営の自由度が高い
合同会社の場合は、会社の事情に合わせて定款で組織のあり方を決めることができます。これは「定款自治」ともいわれ、合同会社の自由度や意思決定のスピードにつながるメリットです。
たとえば「出資だけする人」「出資と経営両方を行う人(業務執行社員)」を分けることや、代表社員を定めるか否かなども柔軟に考えることができます。
さらに出資者と経営者は同一であるため、株式会社のように株主への説明や決議をあおぐ工程がいらず、事業の意思決定がスムーズです。経営実態を握る人が直接かじ取りをすることができます。
節税効果などの恩恵を得られる
合同会社をはじめ、法人化すると個人事業主にはない大きな節税効果を得られます。法人化すると経費の範囲が広がったり、納める所得税が軽減されたりするためです。
補助金や助成金といった制度には、個人事業主では利用できないものがあります。法人化していればさまざまな制度が活用でき、事業に役立てることが可能です。
合同会社として法人になれば、課税事業者になった際に消費税の免除期間があるのも見逃せません。そもそも課税事業者になるべきか迷っている場合は「インボイス登録ガイド(無料)」を参考にしてください。職種別に登録の是非がわかります。
デメリット
こちらでは、合同会社を設立するデメリットを解説します。
資金調達の選択肢が少ない
合同会社には株式がないので、株式を買ってもらう出資など、広く大規模な資金調達はできません。創業手帳の無料相談では「合同会社で出資調達ができるか」という相談もありますが、出資での調達は基本的に株式への出資となるのでできません。
また、ベンチャーキャピタルのように株式上場や値上がりの利益を狙うファンドの投資対象にもなりませんので、資金の調達方法の選択肢は限られます。
とはいえ、融資や寄付購入型のクラウドファンディング、ファクタリングなどの資金調達は可能です。調達できる金額の中で事業を行えるのであれば、合同会社でもよいということになります。
冊子版の創業手帳では、創業時の融資先としておすすめな日本政策金融公庫の融資制度について、詳しく解説している資料を無料配布しています。融資成功率を上げるコツも必見です。
出資者の関係構築が必要になる
合同会社で出資者が複数いる場合、関係構築が欠かせません。議決権や利益の分配に出資額が絡まないゆえに、何を基準として決議するのか、利益を分けるのかを明確にしておく必要があります。
基準をしっかり決めておかないと、誰かが満足できない配分になったり、対立して収拾できなくなったりし、経営維持にもマイナスです。
良好な人間関係の構築や、丁寧に合意形成する努力が求められます。議決権や利益の配分について定款に定めておくことも必要です。
知名度・認知度が低い
合同会社は2006年に創設された制度なので、まだ20年に満たないほどの歴史しかありません。そのため世間的には知名度が低く、信用してもらいにくくなります。
合同会社の代表者を定めた場合の肩書は「代表社員」です。「代表取締役」という表現は使えないため、人によっては肩書を見てもピンとこないケースがあります。
お客様から「何かが合同してできた会社なんですか?」と聞かれたりするだけでなく、場合によっては融資などの資金調達にも影響しかねません。
権利譲渡・相続・事業承継がしにくい
合同会社は会社法第585条1項にもとづき、社員すべての合意がない限り社員の持ち分の一部または全部の譲渡ができません。事業承継も同様で、合同会社の社長が亡くなっても相続人は相続できず、死亡した社員は退職扱いになってしまいます。
相続させたい場合は、定款に「出資者の地位が相続の対象となる」と書き加えておかなくてはなりません。一人社長が死亡すると会社は解散になるため、会社の消滅を防ぐために社員を複数にしておくことが必要です。
株式会社のメリット・デメリット
株式会社のメリット・デメリットをご紹介します。詳しくはそれぞれ解説していきましょう。
| メリット | ・資金調達のしやすさ ・社会的信用の高さ ・経営の継続性・承継のしやすさ ・人材確保の有利さ ・経営権と出資の分離 |
| デメリット | ・設立費用が高い ・維持コスト・事務負担がかかる ・意思決定に時間がかかる |
メリット
株式会社には、資金調達や信用力といった大きな強みがあります。ここでは、起業や事業拡大を目指す方にとって魅力的なメリットを具体的に紹介します。
資金調達のしやすさ
株式会社は株式を発行して出資を募ることができるため、大規模な資金調達が可能です。さらに金融機関やベンチャーキャピタルからの融資や投資も受けやすく、成長スピードを加速させやすい点が大きな魅力です。
合同会社と比べると資金面での選択肢が広がるため、将来的に事業を拡大したい起業家にとって有利な法人形態と言えます。資金調達力の高さは、安定した経営基盤を築くうえで欠かせない要素です。
社会的信用の高さ
株式会社は広く社会に認知された法人形態であり、取引先や顧客から安心して契約できる相手と見られます。特に法人間取引では「株式会社であること」が信用の一つの基準となるケースが多く、大手企業や行政機関との契約にも有利です。
結果として事業拡大のチャンスが広がり、安定的に会社を成長させたい起業家にとって大きな魅力となります。
経営の継続性・承継のしやすさ
株式会社は株式を譲渡することで経営権を移転できるため、事業承継や世代交代がスムーズに行えます。代表者が変わっても法人自体は存続するため、取引先との契約や社会的信用も維持されます。
これは個人事業や合同会社にはない強みであり、長期的に会社を存続させたい経営者にとって大きな安心材料となります。将来的に後継者へ事業を引き継ぐことを視野に入れている場合、株式会社の仕組みは非常に有効です。
人材確保の有利さ
株式会社は社会的な認知度が高く、求職者に安心感を与えるため、採用活動で有利に働きます。さらに将来的に株式上場を目指せる可能性があることから、成長志向のある優秀な人材にとって魅力的な選択肢となります。
また、ストックオプションなどを用いたインセンティブ設計も可能であり、社員のモチベーション維持や長期的な人材確保に役立ちます。人材は会社の成長に不可欠なため、この点は大きな強みです。
経営権と出資の分離
株式会社では出資者である株主と経営を担う取締役が明確に分かれており、所有と経営を分離できる仕組みを持っています。オーナー自身が経営に関わらなくても、専門性を持つ経営者に運営を任せられる柔軟性があります。
また、株主は出資比率に応じて影響力を持ちつつ、日常的な経営判断は取締役が行うため、効率的で専門性の高い経営体制を築くことが可能です。これにより企業の持続的な成長を支えられます。
デメリット
株式会社には多くのメリットがありますが、一方で設立や運営に伴うコストや手続き面での負担も存在します。ここでは、特に注意すべき3つのデメリットを解説します。
設立費用が高い
株式会社を設立するには、定款認証のための公証人費用や登録免許税などが必要で、最低でも17万円前後のコストが発生します。合同会社と比べると倍以上の負担になることもあり、創業初期には大きな出費となる点は注意が必要です。
ただし、この初期投資によって社会的信用度が高まるため、資金調達や取引のチャンスを得やすくなるというメリットもあります。費用をデメリットと捉えるか、将来の投資と考えるかが重要です。
維持コスト・事務負担がかかる
株式会社は設立後も毎年の決算公告や株主総会の開催、登記事項の変更など、法的に義務づけられた手続きが多く存在します。専門家に依頼する場合には顧問料や手数料が発生するため、維持コストも一定額かかる点が特徴です。
小規模事業ではこの事務負担を重く感じることがありますが、近年は会計ソフトや専門サービスを利用することで効率化も可能です。適切な外部支援を活用すれば、負担を最小限に抑えられます。
意思決定に時間がかかる
株式会社では重要な経営判断を取締役会や株主総会で決定する必要があり、オーナー一人の判断で迅速に動けない場合があります。特に複数の株主がいる場合は意見調整に時間を要し、スピード感が求められるビジネスではデメリットとなり得ます。
ただし、こうした意思決定プロセスは経営の透明性や公正性を高める仕組みでもあります。成長段階に合わせてガバナンスを整えることが、健全な経営に繋がります。
合同会社を作るなら”ココ”にこだわるべき

メリットとデメリットを理解し、合同会社のイメージが固まったら、こだわるべきポイントも知っておきましょう。
最初でつまずかないよう、設立前に入念な準備が不可欠です。
定款に定めるルール
合同会社を立ち上げる際は、議決権や利益の分配方法など、揉めやすい要素を定款にしっかり定めておくのが大切です。
定款には「任意的記載事項」という項目があります。法的に記載義務はないものの、会社独自のルールを設けたいときに書いておけば、効力が認められる要素です。
合同会社の立ち上げ時には任意的記載事項を活用して、決まりごとを定めておきましょう。特に複数人の出資者がいる場合、多少細かくてもトラブルを防ぐために必要となります。
業種や事業の適合性
業種や事業との適合性を踏まえて合同会社を立ち上げるのもポイントです。合同会社のメリットが最大限に活かせるかを考えてみましょう。
たとえば一人社長や個人事業主から法人成りしたいときは、リスクを少しでも減らすのが得策です。設立や維持のコストが低い合同会社ならリスクヘッジになり、適合性が高いといえます。
業種でいえば、小規模でも始めやすいIT・Web系の事業、コンサル業、個人のスキルを活かせるクリエイティブ業なども相性がいいでしょう。
資金調達の可能性と方法
合同会社は株式会社に比べて資金調達の方法が限られています。そのため設立後に資金調達の可能性はあるのか、ある場合の方法も検討しておくのが無難です。
資金調達の可能性をはかるには、具体的な事業計画を策定した上で必要な資金を試算しておきます。
社員の出資や自己資金だけで十分なのか、融資や補助金などを見越して考えるのか、事業計画をもとに練っておきましょう。
合同会社設立までの具体的な手順をわかりやすく解説

定款の作成や必要書類の準備など、合同会社を設立する手順を解説します。
- 定款作成
- 資本金の払い込み
- 登記書類の作成
- 登記申請
- 登記後の各種行政などへの手続き
下記で詳しく説明していきます。
1:定款作成
会社名、本店所在地、事業の目的、資本金額など、法人設立に必要な事項を決め、定款を作成します。
定款は作成義務はありますが、登記の際に公証人の認証無しで法務局に提出可能です。
2:資本金の払い込み
資本金を出資者の口座に払い込みます。まだ法人が設立できていないので、この段階では出資者の個人口座に払い込んで構いません。
3:登記書類の作成
法務局に提出する書類の作成と、必要な書類を準備します。
登記申請書、登記すべき事項、定款、印鑑届書などが必要です。
| 必要なもの一覧 |
|---|
| 会社設立登記申請書 |
| 定款 |
| 印鑑届書 |
| 代表社員就任承諾書 |
| 本店所在地決定書 |
| 登記用紙と同一の用紙 |
| 社員の印鑑証明書 |
| 払込証明書 |
| 収入印紙 |
4:登記申請
作成した登記書類を法務局に提出します。
このとき登録免許税を納付するのに、金額分の収入印紙が必要になります。登記申請書を法務局に提出した日付が会社設立日となりますが、登記手続きの完了までは数日かかります。
5:各種行政などへの手続き
登記手続き完了後、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険関係(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク)などに必要な手続きを行います。
なお、より詳しく具体的な手順を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
合同会社から株式会社への移行は可能?
合同会社でスタートしたけれど、途中で株式会社に変えたくなった……そんなときは、会社形態の移行が可能です。
組織変更の手続き・費用
移行の際に必要な準備を押さえておきましょう。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 移行にかかる費用 | ・公告費用:約3万円
・登録免許税:約6万円 |
| 移行に必要なもの | ・組織変更計画書
・登記申請に必要な書類 |
| 移行の手続き | ・全社員から組織変更計画書の承認を受ける
・債権保護手続きをする ・登記申請する |
どのタイミングで移行すべき?
合同会社の規模が大きくなってくると、株式会社へ変更した方が得られるメリットが多くなります。資金調達の広範化や信用度の向上など、企業の持続的な発展を目指すなら移行を検討しましょう。
まとめ・合同会社と株式会社の違いを理解して最適な形態を設立しよう
合同会社を設立する際は、創業メンバーや出資者・投資家などと、会社との関係のあり方や将来像をイメージしながら選択しましょう。
創業手帳では、会社設立について有益な情報をWEBでも数多く提供していますので、無料相談などを含めぜひ利用してみてください。
起業に必要なものは幅広く、漠然としがちです。冊子版の創業手帳で必要なものを一つひとつチェックすると、ビジョンが明確になります。起業家のインタビューを参考に、起業後の自分をイメージすることも可能です。
起業の準備は時系列に整理しましょう。無料の創業カレンダーでいつなにをするかを書き込み、順番にこなすだけでスムーズに起業準備が進みます。
(執筆:創業手帳編集部)
創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。